

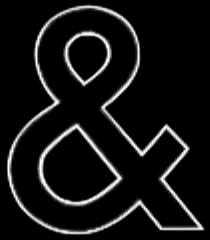

車に依存しないカー・レス社会の実現に向けてシンガポールでは、自動運転車(AV)やカー・シェアリングなどモビリティ分野の様々な取り組みが行われています。都心部の植物園「ガーデン・バイ・ザ・ベイ」で2019年10月に始まったオンデマンド型の自動運転のシャトルバスの運行も、そうした取り組みの一環です。カー・レス社会に向けた取り組みと、その背景について、ジェトロ・シンガポール事務所 調査担当の本田さんに寄稿いただきました。
Profile:本田 智津絵(ほんだ ちづえ)さん
ジェトロ・シンガポール事務所 調査担当
総合流通グループ、通信社を経て、2007年にジェトロ・シンガポール事務所入構。共同著書に『マレーシア語辞典』(2007年)、『シンガポールを知るための65章』(2013年)、『シンガポール謎解き散歩』(2014年)がある。
ガーデン・バイ・ベイ内を運行する自動運転シャトルバス「オート・ライダー」は現在、園内の1.5キロのルートをゆっくりと走行しています。専用アプリで予約することができ、夜になれば、車内と車体に鮮やかなライトが投影されるなど、人気観光アトラクションの一つともなっています。運行するのは、シンガポール政府系総合エンジニアリング会社のSTエンジニアリング(以下、ST)、大手高速バス運行会社のWiller(ウィラー、本社:大阪)と三井物産のシンガポール子会社でカー・シェアリング事業を展開するカー・クラブの3社。使用する車はフランスのナビヤ(Navya)が設計・製造と、シンガポール、日本とフランスの3カ国が係わる国際プロジェクトでもあります。

STが自動シャトルバスの運行に取り組むのは、今回が初めてではありません。同社は2015年から同植物園で自動運転のバスの運行を開始していました。2019年10月から始まったウィラーとカー・クラブとの共同運行では、エンターテインメント要素を取り入れた新しい形のサービスです。また、STは2019年8月20日から、セントーサ島でも一般乗客を対象にオンデマンド式によるシャトルバスの実証実験を3カ月間行いました。ガーデン・バイ・ザ・ベイとセントーサ島でのオンデマンド式シャトルバスを含め、シンガポールのAVの水準は現在、「レベル3」の段階にあります。レベル3とは、運転が自動化しているものの緊急時にはドライバーが対応する段階を指します。
STのほかにも内外各社がAVの実証実験を国内で行っています。米国スタートアップのニュートノミー(nuTonomy)が2016年8月から、公道での自動運転タクシーの実地実験を行っています。また、地場公共輸送会社コンフォートデルグロが2019年7月30日から、シンガポール国立大学(NUS)のキャンパス内で、仏スタートアップのイージーマイル(EasyMile)が開発した自動シャトルバス(定員12人)の運行を始めました。
国内各地で進むAVの実証実験は、政府が2014年11月から始めているスマート国家(Smart Nation)の取り組みの一環でもあります。「スマート国家」構想とは、最新のデジタルテクノロジーを活用して自国の社会課題を解決して、豊かな暮らしを実現すると同時に、新たなビジネス機会の創出を目指すものです。AV導入を含むモビリティ改革の取り組みは、このスマート国家構想の下、国家戦略プロジェクトの1つと位置付けられ、2020年代初頭にも公共輸送にAVを実験的に導入することを目標としています。
シンガポールがモビリティ改革に取り組む背景には、限られた国土の中でモビリティの効率化に迫られていることがあります。都市国家である同国の国土面積は725.6平方キロメートルにすぎません。そのうち道路が占める面積は全国土の約12%。政府は1990年から、自動車購入の際に自動車所有権証書(COE)の購入を義務付け、同証書の発行枚数を通じ自動車台数の伸びを調整してきました。ただ、限られたインフラの中で、さらなる人口と自動車の増加に対応するには、安全でかつ、効率的なモビリティの実現が課題となっています。またシンガポールは、バスの運転手不足と人口高齢化という日本と同じ課題も抱えています。運転手の人手不足を解消して、高齢者の輸送手段を確保する手段の一つとして、AVは期待されているのです。
このほか、政府がモビリティ改革の一環として比較的に早い段階から導入を始めているのが、グラブ(Grab)に代表されるカー・シェアリングです。グラブは元々、2012年にマレーシアで創業したスタートアップですが、2013年にシンガポールに本社を移すと共に、タクシーの配車サービスを開始しました。グラブはその後、契約ドライバーが運転するグラブカーや、シャトルバスなど多様な配車サービスを展開しています。グラブは2018年3月、競合の米ウーバーの東南アジアの配車とフードデリバリーの両事業を買収する代わりに、ウーバーはグラブの株27.5%を取得しました。この結果グラブは、シンガポールを初め、インドネシア、フィリピンなど東南アジア8カ国339都市で展開する域内最大の配車サービス事業会社へと成長を遂げています。
カー・シェアリングは、グラブが登場する2013年以前からシンガポールでは存在していました。上掲のガーデン・バイ・ザ・ベイでのAVの運行にも係わるカー・クラブは1997年、2018年8月時点で約270台の車両を保有する国内でも最大の会員制の自動車シェアリング・サービス会社です。しかし、アプリというデジタル・プラットフォームを活用した自動車のシェアリング・サービスが本格化したのは、グラブなど配車事業会社が相次いでサービスを開始した2013年以降のことです。
カー・シェアリングの普及によって、車の所有のあり方は変わってきています。陸上交通庁(LTA)の統計によると、グラブが配車サービスを始めた2013年の乗用車(自家用車、法人所有の車を含む)は60万7,292台でしたが、2019年には55万5,450台にまで減少しました。また、タクシーの台数も2013年には2013年には2万7,695台だったのが、タクシー運転手がグラブなどの契約運転手へと切り替える動きが増えた結果、2019年末に1万8,542台にまで減少しました。一方、配車サービス会社が契約するレンタカーは、2013年の1万3,919台から2019年に7万7,141台へと大きく増え、車の所有の概念が変化しつつあることがわかります(図参照)。

このほかシンガポールの北西部テンガで開発予定の公団住宅地域は、国内初のカー・ライトな街となります。街の中心部では車が通る道を全て地下に建設して、地上は歩いたり、サイクリングしたりしやすくなります。
自動運転やカー・シェアリング、そして歩行者に優しい街づくりと、カー・レス社会に向けた様々な取り組みが進んでいます。
RECOMMEND:
・スマートネーション「シンガポール」では、新たな市場が日々生まれている
・NUSの自動運転シャトルバス「EZ10」について